305)『自分の中に毒を持て<新装版>』を読んで

2025年の大阪夢島万博が開催されている。
大阪での2回目の万博であるが、大盛況だった第1回目の大阪万博がきのうのことのように思い出される。月の石やロボットがシンボル的な存在であったが、岡本太郎の「太陽の塔」も賛否両論、大きな話題になった。
私自身も、あの大きなだけの、奇々怪々なシンボルマークには美しさも面白さも感じなかった。作者が「芸術は爆発だ!」と豪語する人物だけに、「そういうものか」と受け入れていった人々も多かったのではなかろうか。
その岡本太郎が2017年に出した本が、2025年に「新装版」となって本屋の店頭に並んでいる。真っ赤なカバーがかけてあるその本のタイトルは『自分の中に毒を持て』である。
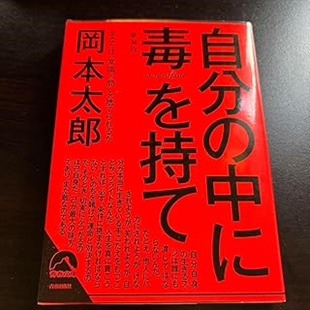
もうご存知とは思うが、ちょっとだけ岡本太郎の経歴に触れる。
岡本太郎は1911年に神奈川県川崎市に生まれ、1996年に逝去。太郎の父親は政治・社会の風刺漫画家岡本一平、母親は歌人であり小説家である岡本かの子である。
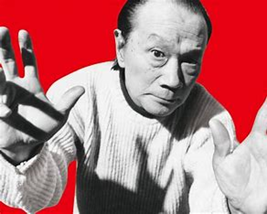
岡本太郎については、岡本太郎記念館の館長、平野暁臣氏の紹介が簡潔で分かりやすい。(サイカルjournal NHK)
平野館長の紹介の主要部分を紹介しておく。それだけでも岡本太郎の信念や考え方が分かる。
- 岡本は、作品のジャンルや表現領域が驚くほど広い。美術作家の普通は“一点主義”。
- 岡本の底流にあったのは、「芸術は大衆のもの」という思想。
- 岡本はパブリック・アートを数多く残した。(パブリック・アートとは美術館や画廊ではなく、公園などの公的な場所に設置されアート作品のことを言う。)
- 岡本はパブリックアートに力を入れた。芸術作品を自分で買うことができなくても、いつでも誰でもまるで自分の所有物のように作品を見ることができた。
- 岡本太郎は作品を売らなかった。売れてしまったら、それこそ大企業の社長室や金持ちのリビングに入ってしまう。岡本は自分の代表作全てを持って、全国で「岡本太郎展」を開いた。そこへ行けば人は、太郎の代表作品を全部見ることができた。

・・・・・・・・・・・
では、新装版『自分の中に毒を持て』の内容に移ろう。本書は章ごとのサブタイトルだけでも、かなりセンセーショナルである。
第1章 意外な発想を持たないとあなたの価値は出ない -迷ったら危険な道に賭けるんだ
第2章 個性は出し方 薬になるか毒になるか -他人と同じに生きていると自己嫌悪に陥るだけ
第3章 相手の中から引き出す自分 それが愛 -ほんとうの相手をつかむ愛しかた愛されかた
第4章 あなたは常識を捨てられるか-いつも興奮と喜びに満ちた自分になる
岡本の本は書き方が断言的で、指示や命令の表現を多く使っているので、強く響く。しかし、今回本書を読んで、私が年をとったためか、自分自身のとらえ方が変わってきているのを感じる。彼の見つめているところが根源的なところであり、岡本は読者に寄り添って、その身になって提言しようとしている。岡本氏の過激な表現にも、その底に脈打つ一途さ、あたたかさが感じられる。
彼が一貫して言っているのは、次のことである。
「何を試みても、現実ではうまくいかないことのほうが多いだろう。でも、失敗したらなお面白いと、逆に思って、平気でやってみればいい。とにかく無条件に、生きるということを前提として、生きてみることをすすめる。」
「才能のあるなしにかかわらず、自分として純粋に生きることが人間の生き方なのだ。」
岡本太郎はたぶんに正直すぎる、率直すぎる人間なのかもしれない。その熱い(熱すぎる)人間性のため、我々市井人には誤解してしまうものがあるのかもしれない。
